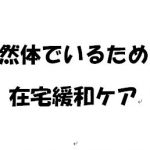病院の外にでないとわからないことがある。
こんにちは、本日も朝から外来診療の札幌の医師@今井です。
MRICのこの記事の内容良く理解できますね。しばし医療者って病院の中の世界=患者さんにとってもそれが全ての世界と考えがちですが全然違います。
むしろ病院の外の世界が主体で医療なんて生活の中の、人生の中のほんのわずかな部分しか占めていないのに病院にいると勘違いしてしまうんですよね。
MRICのこの記事そのことがよくわかる良い記事です。是非一読ください。
MRICより
Vol.080 地域に出てみないと見えないもの
帝京大学大学院公衆衛生学研究科
高橋謙造
2018年4月16日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
しかし断言しよう。地域に関わらないと得られない学びがあるのだ。
自分のたった2年半弱の離島経験だけでも、一般の大病院勤務ではとても得られない学びがあった。今回は、その経験を共有したい。
当時、徳之島に赴任した時に、院長、医局長と相談して、週一回の当直ローテーションに入れていただくことにした。大学小児科から派遣された身だから、小児科のみに特化したい、と言えばそれも出来た。しかし、赴任当日に運ばれて来た外傷患者さんの緊急手術を手際良くこなす先生方に圧倒され、術者と息の合ったペースで鮮やかな手つきで縫合を進めていく二番立ち助手の先生が実は内科医だと知り、「こんな環境なら、少しでも幅広く学びたい。」という気持ちが強くなったためだ。
それ以後の半年は、院長や医局長とのチームで当直に週一回入り、まずは私が呼ばれる(ファーストコール)という形式になった。200床満床の病棟もみつつ、外来もみるのだ。
最初は患者さんを診るたびにヘルプコールをしていたが、スタッフの皆さんの補助のおかげもあり、半年も経つと外傷の縫合などもかなり丁寧に出来るようになった。また、病棟の患者さんが急変した際にも、適切に処置や説明が出来るようになった。
当直時にはエコー室に出入りし、自分を被験者にして心エコーの練習をしていた。「もし先天性心疾患の子が来たら、診断出来るだろうか?」という不安があったためだ。
また、CT室によく出入りして、当直の放射線技師さんからCTの読み方を教わった。その日の昼間にあった症例で勉強になる画像を出して、説明してくれた。夜間には、どんな患者さんが来るか予測も付かない。嘔吐している患者さんのCTを撮っていた技師さんが、大動脈解離の存在に気づき、私に伝えてくれたこともあった。
そして、入職半年後には単独当直を命ぜられるまでになった。当直の最中に入院させた患者さんは、自分が主治医となるのがルールであった。そのため、小児科病棟の小児の受け持ちに加えて、成人、高齢者の主治医も経験した。
ある冬の時期に、救急車で運ばれて来た80代のおばあがいた。救急隊の方から、「先生よ、このおばあよね、耳が遠いみたいだからよ、あまり話が通じんよ。」と言われた。
診察と画像診断の結果、軽度の圧迫骨折による痛みのせいで歩けない事が分かった。親族は、島の反対側の町におり、そんなに頻繁には来院できなかった。
実質的に独居であったおばあの主治医は大変だった。診察に行くたびに、「痛いのを早く治せー!このヤブ若造が!早く家に帰せー!」という罵倒を繰り返す。しかも、耳は遠いので、こちらが何か言い返しても通じない。診察に行くたびに敵意を持った目で睨まれて罵倒されるのを繰り返すと、段々気が滅入って来る。そんな時間が2日ほど経った日に、病棟の看護師さんから、「先生、筆談してみたらどうね(筆談してみたらどうですか)?」というアドバイスをもらった。
早速、島出身の看護師さんに同行してもらい、入院時に口頭で伝えた(つもりになっていた)内容を再度説明した。今の状態(圧迫骨折)、治療の方針(カルシトニン注射による痛みコントロール)等について伝えた。私が書いた内容は、看護師さんが島口(島独特の方言)で説明してくれた。耳が遠いはずのおばあであったが、島口で話すとある程度コミュニケーションが取れるようで、おばあの表情は少しずつ和らいだ。しかし、今後の見込みの段階になり、入院は最低でも1ヶ月程度と伝えると、表情は再び厳しくなり、「うら(あんた)、早う帰さんか!」と怒りの感情を露わにした。それでも、「痛みが落ち着かないと、歩けるようになるかどうかも分からない。」と看護師さんに伝えてもらうと、今度は手を顔の前に合わせてボロボロと涙を流しながら懇願していた。
それからは、毎日回診に行くたびに、おばあが話し言葉で訴え、それを私が筆談で返答する、そんなやり取りが始まった。おばあの訴えかけは真剣だった。
「まだトイレに行くのも痛くて難しい。でも、歩きたい。まだ帰れないだろうか?」と聞いて来る。診察で腰を軽く押すと、「あがっ(痛っ)!」と声をあげる。この痛みではまだ歩けないだろうと判断し、「痛み止めを増やす?」と書いて伝えると、「いや、要らん、好かん!薬に頼ったらおしまいじゃ!」と怒り出す。「じゃ、今のままで頑張れる?」と書くと、ボロボロと泣き出す。回診は、毎回この調子だった。
入院して10日が過ぎた頃、病棟から、「先生、〇〇さんね、一人でトイレに行けよったみたいよ。頑張ったわ。」との話が来た。10日で改善するとは早すぎないかと思いつつ、さっそくおばあの病室に行き、「一人でトイレ行けたの?」と聞くと、おばあの表情は暗かった。「先生よ、まーだ、ふしやむいっちょ(痛いのよ)。」と言う。いつの間にか、「うら(あんた)」が「先生」になっていた。
「でもね、歩けたのはいいことだよ。きっと元気になるよ。」と伝えると、おばあの表情は少し明るくなった。
この後、経過を院長に報告すると、「島のじじばばは、普段から野良仕事しとるからね。治りも早いはずよ。あんまり入院長引かせんで、家に返してあげた方がリハビリにもなるよ。」とのアドバイスだった。現場を知っている医師の言葉には説得力があった。
そして、12日目。回診に行くと、おばあはベッドサイドに腰掛けて外を眺めていた。背筋がぴんと伸びていた。痛みが残っていれば、その姿勢は取れないはずだ。「おばあ、痛くないね(痛くないの)?」と聞くと、こちらを向いてにっこりと笑ってうなずいた。腰を押さえても痛がらない。いよいよいけるかなと考え、「お家に帰ろうか?」と書くと、目を大きく見開き、うんうんとうなずいた。と同時に、涙を溢れさせ、またもや手を顔の前に合わせて拝むようにしてくれた。
それからは、おばあのことは訪問看護部署に引き継ぎ、訪問看護担当は内科の先生方に任せることになった。その年はインフルエンザの大流行や低出生体重児への対応などがあって、かかりきりになってしまっていた。
インフルエンザの流行が終息した頃に、院長から声がかかった。「先生、訪問看護を手伝ってみんね(手伝ってみないかい)?」との話であった。退院した患者さんたちの自宅での生活を知ることができる願ってもないチャンスだったので、この誘いに飛びついた。
訪問看護では、数件の家を毎週訪問することになった。ある日、訪問看護部の看護師さんと一緒に出かけた時のことだった。「今日は、先生が主治医なさってた〇〇さんのうちに行きますよ。」とカルテを手渡してくれた。あの、耳が遠いおばあの家だった。
車は、病院から1時間ほど走り、ある岬の突端近くで止まった。
そこには、本当に粗末な小さな家があった。
その家の軒先で、あのおばあは前かがみになり、野菜を干していた。
看護師さんと私の顔をみると、笑ってうなずいてみせた。
二人で軒先から家にあがり、看護師さんは血圧を測る準備をした。
おばあは、棚からごそごそと折りたたんだ紙の束を出し、看護師さんの前に差し出した。
それは、私が書いた筆談の紙の束だった。大事に取っていてくれたのだ。
看護師さんは、「この紙を見せてくれるんですよ。経過が分かるようにって、毎回ね。まあ、ちょっと物忘れが進んでるのもあるみたいで。」
血圧測定が終わると、私の診察の番になった。
私は、カルテ用紙を一枚外し、「腰はいたくない?」と書いた。
すると、おばあは驚いた様に私の顔を見て、かつての主治医だった私に初めて気づいたようだった。
「ええ、ええ、ひんま(昼間)はいいよ。おぼらだれん(ありがとうございます)。」
訪問看護でも、独居のおばあにとっては嬉しい来客だったのだろう。
診察が終わると、おばあは寂しそうだった。
お茶を出してくれて、飲み終わる前に、また注いでくれる。
お茶うけに、パパイヤの漬物や、黒糖など色々と出してくれた。
それでもお暇しなければならない時間がやって来た。
軒先を後にする時に、「先生、はって、見ていきやい(畑を、見ていって)。」と声をかけて来た。
おばあと三人で、岬のより先端の方に歩いていくと、波の音が強くなった。
そして、そこには一面のお花畑があった。
優しい赤色が舞うお花畑だった。
その時に、これまでの全てが理解できた。
あぁ、おばあはこのお花畑が守りたかったのだ。
それで、必死になって歩く努力もして、早く帰りたがったのだ。
今ここに来なければ、おばあの涙の本当の理由にも気づくことが出来なかった。
おばあは、自分が大事にしている「生活、生き方」を見せてくれたのだ。
この季節になると、今でもあのお花畑は花を咲かせているだろうか、といつも考える。
自分の中では、今でもあのおばあとお花畑は変わっていない。
今でも、島に戻れば、またおばあと一緒にお花畑を見れそうな気がしている。
医療人類学によれば、病気というものは、生物学的なDisease(疾病)と社会的、心理的なIllness(病い、病み)に別れるという。
おばあのDiseaseは圧迫骨折であり、Illnessは、「お花畑を枯らしてしまう」という心配事だったのだ。
http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/070523illness.html
病院に張り付いて患者さんを見ていれば、Diseaseの診断・治療の専門家にはなれるだろう。
しかし、Illnessにまで踏み込んで医療に関わろうとすれば、生活を知らなければならない。
そして、地域に深く関わっていかなければ、生活は見えてこない。
地域に関わっていくことは、医療者としてIllnessにまで関わっていくことなのだ。
どうでしょうか?良く理解できますよね。離島でなくても札幌でも東京でもここに書かれている、言いたい内容は同じですよ。いつまでも病院の中にいないで一歩外に踏み出してみませんか?
現在医師募集中→こちらをどうぞ!
外来や訪問看護、地域で活動したい看護師さんも→こちらをどうぞ!