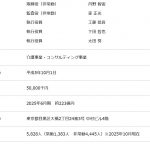死生観、意思決定について
MRICの記事で大変面白い記事をみましたので紹介致します。小松先生の記事は大変勉強になるため、この1年くらいMRICに書かれたものはなるべく読むようにしていました。今回は死生観やターミナルケアにおける意思決定の中で医師の果たす役割などについて書かれています。在宅でのターミナルケアにおいては治療方針などの意思決定は現在は主治医と本人、家族などで決定していることが多いですが今後在宅医療の現場でもどんどん思決定が困難な人、家族が増えてくることが予想されます。その際のキーワードは<多職種が参加する医療チームによる議論>だと考えていますが皆さんはどう考えますか?
Vol.040『地域包括ケアの課題と未来』編集雑感 (12):卒業論文にみる死生観
医療ガバナンス学会 (2016年2月13日 06:00)
(ソシノフブログhttp://www.socinnov.org/blog/p505より転載)
小松秀樹
2016年2月13日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
———————————————————————
●ターミナルケアでの齟齬
『地域包括ケアの課題と未来』で、小野沢滋医師は、入院中の決定が本人と近親者に与える影響を書いた。人は誰でも人生の終末期に大きな病気で入院することになる。高齢になればなるほど、病気は治癒しにくくなる。亀田総合病院から退院する患者の30%は要介護状態で退院するが、その半数は新たに要介護状態になったという。入院中の決定が患者と家族のその後に大きな影響を与える。胃ろうを造設すると多くの患者は自宅に帰ることなく生涯を終える。治療のやめ時を失う場合も少なくない。本人は意思決定できる状況になく、家族は決定がどのような結果をもたらすのか分からない。急性期病院の医師は生命維持を使命としており、決定が要介護者のその後の生活、家族に及ぼす影響を知らない。
ジャーナリストの熊田梨恵氏は、胃ろうに関する問題をまとめた。彼女には『胃ろうとシュークリーム』(ロハスメディア)という著書がある。胃ろうという手段と介護の重さがもたらすどろどろした現実が描かれている。
私の体験を紹介する。86歳の認知症男性に対し嚥下困難のため胃ろうを勧められた。妻が断ったところ、主治医は安楽死ですかと返した。妻は親族に、医師が安楽死と尊厳死の区別ができていないと不満を漏らした。主治医は、胃ろうがだめならと、栄養補給路として鼻から胃に管を挿入した。男性は、胃管を嫌がり抜こうとするので、ベッドに縛り付けられた。妻は、縛り付けられて生きることを悲しんだ。ほどなく、男性は死亡した。
高齢者の治療をどこまで行うのか、胃ろうに代表される生命維持のための手段をどこまで使うのか、終末期の患者をどのように支えるのか、本人、家族、医療者の知識はさまざまであり、希望もさまざま。しかも、意思疎通が乏しい。全体をまとめ上げる枠組み、方法があるのか。広く喧伝されているのは、死生観である。死生観を振りかざすことで解決できるのか。
●卒業論文
以下、ネット上で見つけた「医療を支える死生観」(橘尚美『関西学院大学社会学部紀要第97号』)を紹介する。関西学院大学社会学部の卒業論文である。内容的には専門家というより一般人の考えを代表しているように感じた。優秀論文として評価され安田賞を受賞した。以下の記述は、他の著者からの引用を含むが、本人の考えに近いものと思われた。
●主観的記述
「(看取るとは)『死に逝く人の生』を共に生き、その人の生に参加することであらねばならない。」
「人間の共通する運命である死を真剣に考え、死に対して成熟した態度を身につけていなければならない。」
「医療従事者は、個々の患者について、身体、心理、社会全般にわたる深い次元で理解する必要があるのだ。そして、ターミナルケアは、この全人的医療の延長線上にあるものである。」
「(死生観とは)『宇宙や生命全体の流れのなかで、個(私)の生や死がどのように位置づけられ、どのような意味をもっているのか、ということについての考え』とでもいったものである。もっと単純に、『私はどこから来て、どこに行くのか』という問いに対して何らかの答えを与えるもの、といってもよいだろう。」
「死を見つめる必要性を押しやってきた戦後の近代合理主義の延長線上にもたらされたものが『死生観の空洞化』といわれる事態である。」
「患者のケアにあたりながら、また、色んな患者の色んな生き様そして死に様を目のあたりにしながら、医療者は死にゆく人から多くを学ぶことができる。」
「『苦しみの中に留まれる力』が現代医療の中に求められているものかもしれない。患者と苦しみを共にするという経験を積み重ねることで、自分自身の限界に向き合い、既存の価値の転換を図ることが重要である。」
「死に対する不安がもともと強い人は霊魂の観念も強く(逆もいえる)、そのような人が死の怖れから解放されるためには、死を肯定的にうけとらざるをえない。つまり、死に対する怖れが強い人にあっては、その怖れは霊魂の観念をもつことによって正当化される。」
「死の不安が軽減され、肯定的な死観を有することで、自分や他者の死に対してより効果的に対処することができるようになる。」
●客観的記述
「年齢が高くなればなるほど逆に死の不安が有意に低くなる。」
「看護学生の不安が最も強く、医師が最も弱く、看護師はその中間に位置する。」
「『転生と復活』という死生観は、(医師が)どの群と比較してももっとも希薄だった。」
●インタビューに対する医師の回答
卒業論文で7人の医師にインタビューを試みている。特徴的な回答を紹介する。
「死を前にした潔さ、見苦しさも見てきました。死は人生の完結であり、集約であると思いますが、本人がいくら慈悲をもって生きた人でも幸せな死を迎えるとは限りません。自然が作るものとして受け止めるように心がけています。」
「自分自身は、生物学的に死は無に帰すと考えていますが、そう思っていない人にはその人の考え方に共感するようにしています。この生物学的死の考え方は、青年期までに培われた、いわゆる『科学的なものの考え方』の故と思います。」「飼っていた金魚が死んでしまったのでお墓を作って土に埋める。しばらく月日がたってそこをそうっと掘り返してみると何も無い。死んだら土に還るんだ、と理解しました。人間だって特別ではない。お墓の土の中で土になっていくんだろうと。」
「生に対する執着が強い患者に寄り添っていく上では、関わる自分自身が死を身近に感じすぎることがあまりよくないと思うこともある。」
●近代合理主義
近代合理主義という言葉が説明なしに使われていた。近代合理主義は、私の理解では、大陸合理主義にイギリス経験主義が統合されたものであり、現代のあらゆる学問の基礎をなす。人間は理性を持っていることが前提であり、理性で明らかに認められることだけを真とする。明らかに正しいことを基礎に先入観なしに、問題を要素に分けて分析・論証し、その結果を統合する。輪廻転生、復活、霊魂は明証的でないので、その存否は、近代合理主義の考え方では学問の対象とならない。ただし、宗教学、すなわち、宗教の体系やそれを信じる人たちを客観的に観察することは学問たりうる。中世ヨーロッパでは、神学の教義に合致しないと異端とされ、場合によっては処刑された。この時代の神学は、近代合理主義が包括する学問に含まれない。福沢諭吉が明治初期に力説したように、知識と徳義は異なる。近代以後の学問は善悪と無関係に知識を深める。
現代医学も近代合理主義の影響下にある。医学は、徹底して分析的である。例えば薬に効果があるかどうかの証明では、無作為に投薬群と偽薬群を分けて、両者の治療成績を比較する。理論が精緻であることや論調の強さは証明とは無関係である。
戦後の近代合理主義の延長線上に『死生観の空洞化』があるという論理には無理がある。日本で、近代合理主義は、戦後に始まったことではない。戦前でも学問では主導的な考え方だった。近代合理主義に則って考えると、「死生観の空洞化」を主張することは簡単なことではない。統計的に立証しようとすれば、「死生観の空洞化」に関連する要素を体系的に分類し、それぞれの要素について、変化の有無を、すでに有用性が証明された適切な方法で測定しなければならない。いくつかの要素で変化を実証できたとしても、「死生観の空洞化」とまとめることが可能であり、かつ、それが「戦後」の近代合理主義の延長線上にあることを納得させるには、さらなる根拠と議論が必要になる。こうした努力なしに「死生観の空洞化」を主張しても、近代合理主義者、すなわち、教育を受けた常識ある日本人には何を意味することか理解されない。
●治療行為の医師にもたらす負荷
橘は、死についての考え方を、良いものと悪いものに分けている。肯定的死観は否定的死観よりよく、死の恐れが大きいより小さいことがよいとする。また、死について考えれば考えるほど死についての迷信や迷妄が払拭され、死の恐れが少なくなっていくとする。患者を看取ることが苦しいことであり、医療現場での「病や死に直面している患者と関わる経験」が自分を高めることになる、それも辛く悲しいほど自分が高められる。
橘の想像の中で、看取りという営為が膨らんで巨大なものになっている。医療現場では、死ぬべき人が死ぬことは日常の世界である。私の経験上、医師は、通常の死を看取る過程を橘が想像するほど大きなものと感じていない。一方、治療の結果が期待したものでなかった時に生じるストレスは耐えがたい。手術の合併症の治療には膨大な時間と労力が求められる。死に瀕した患者を救うために、24時間、寝ている間も様々な可能性を考え続ける。再手術するのか、経過をみるのかギリギリの決断が迫られる。治療のための労力以上に、軋轢が負荷になる。手術を受ける患者、家族は治癒を切望している。結果が期待に反したとき、血相を変えた家族の罵詈雑言に3時間もさらされる。食事はのどを通らず、ほとんど眠ることもできない。場合によっては、刑事事件として扱われ収監されることもある。知人の泌尿器科医は、合併症で患者が死亡した後、体重が10キロ以上減少した。
●看取りの担い手
橘は、患者が治療を第一の目的とする非人間的な環境の中で病み、十分なターミナルケアを受けられないまま亡くなっているとの認識を示した。たしかにその通りである。しかし、重症患者の治療には、膨大な資源、人手、それらを迅速に供給するシステムと場が必要になる。治療のためのシステムは、体に差し込まれたいくつものチューブであり、ピコピコと機械音を発し続けるモニターであり、人工呼吸器である。非人間的に見えるが、治癒を最大の目的とする限り、システムはこうならざるをえない。
戦後一貫して治癒を希求してきたのは、患者・家族である。社会もこれを支持してきた。病気の子どもを病院に連れていかないと、保護責任者は刑事責任を問われかねない。医師の治療優先の考えが、医師の価値観と結びついているとは思わない。疾病の治療に関する論文は確率で論ずるものとして発達した。医師が治療を重視するのは、治療に社会と医師の主たる関心が向いており、医学が治療中心に進歩してきたからである。医師は、治療ルールの枠内で行動しているだけである。医師の価値観はルールとは異なる。死にゆく患者の生活を楽にすることの価値と対立するものではない。生活を楽にすることは、要素が多いので、生物学的医学すなわち分析的科学になじみにくいが、医師にターミナルケアの重要性を認識させるのは難しいことではない。
治療行為は医師に人格を破壊しかねない負荷をもたらし、医師に全身全霊の寄与を要求する。ケアについては、ニーズは多様であり、その情報源は検査結果ではなく主として人である。ケア、特に在宅の高齢者については、医師より適切な主役があると思う。
●死は不可避という認識
橘は論文の結論部分で「私たちがくつろいだ気持ちで死について考えることができるようになれば、生きることもずっと心地よいものになる」と書いている。具体的に何を意味するのか。私は、医師が、個々の患者の死生観に深く関わること、近代合理主義の枠外に言及することは、患者と家族、社会そして医師自身に不利益をもたらしかねないと考えている。前立腺がんのマーカーであるPSAを心配してきた後期高齢者に「心配しなくても、必ずお迎え(死を柔らかく表現しただけで、来世を前提としていない)はきます。年取った分だけ、生まれたときよりお迎えは近くなっています。80歳以上になると半数以上の方が前立腺がんをもっています。あったとしても人並みですよ」と話すと、皆さんニコニコし始める。死が不可避であることを言葉に出して確認するだけでも人は安心する。医療行為のメリット、デメリットを冷静に判断できるようになる。