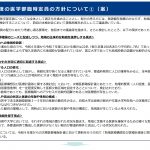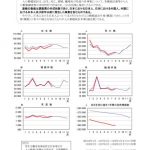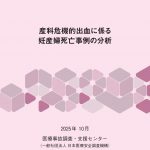「誰もが住み慣れた地域で適切な医療を」・・・本当に可能ですか?【昨年度は約30億円の赤字…JA新潟厚生連病院の立地自治体“財政支援”など県に要望「誰もが住み慣れた地域で適切な医療を」】
こんにちは、札幌のかかりつけ医&在宅医&病棟医@今井です
病院関連の記事で気になる記事を見つけましたのでシェアします。9月4日の記事です。
昨年度は約30億円の赤字…JA新潟厚生連病院の立地自治体“財政支援”など県に要望「誰もが住み慣れた地域で適切な医療を」
「小千谷市や村上市など、JA新潟厚生連病院が地域医療の中核を担う6つの市からなる地域医療連携推進協議会が花角知事に地域医療の維持に向けた支援を要望しました。
昨年度の純損益が30億円あまりの赤字となったJA新潟厚生連。 厳しい経営状況が続き、診療科の縮小や廃止が行われる中、協議会は県に対してJA新潟厚生連への財政支援を継続することや診療報酬制度の見直しを国に働きかけることなどを求めました。 【花角知事】 「県民、誰もが住み慣れた地域で適切な医療が受けられる環境づくり。知恵を出し合いながら、連携してしっかり取り組んでいきたい」 【地域医療連携推進協議会 宮崎悦男 会長】 「(知事から)財政支援の具体的なところについては、まだ言及がないが、重く受け止めていただいたと認識している」」
1医療者として社会保障制度について現在と未来について考えると、現状施政者が言うべきなのは
誰もが住み慣れたで適切な医療が受けられるのは幻想で、住む場所によって受けられる医療の質が異なる時代が来るので各自自己責任できちんと準備を!
だと思います。
厳しいですか?でもこれが現実何だと思います。現実をみせようとしない言動、今井は政治家としてはあまりよくないのかなと。見たくない現実でも認識させる、もしくは認識させなくてもそのためにリーダーは一人でも行動するっていうのが本当のトップのあるべき姿ではないでしょうか?
住み慣れた地域である程度の医療を受けることは可能な体制を国はつくろうとしています。ただ、その量、質に関しては地域によって千差万別です。地域によっては高度医療を受けられることも難しい地域もでてくるでしょう。小児や産科などもない地域も当然出てきます。在宅医や訪問看護師の人的リソースもかなり厳しい地域も当たり前のように見られるでしょう。
どこに住むかで受けられる医療が変わってくる・・・この認識は全国民がきちんと理解しておくべきではないでしょうか?そうしないとこれからの限られた予算の中での効率的な社会保障制度の構築の合意が難しくなりますし、何より地域に住む一人一人の医療に対する想いがばらばらになったまま2040年、2050年になってしまうと思います。結局それって現場にしわ寄せくるんですよね・・・・
皆さんもそう思いませんか??
-
-
時間ある方は以下の項目をチェック!!
法人のこれまでのこと、これからのことを確認したい人はこちら↓
直近のいまいホームケアクリニックの診療実績について知りたい方はこちら↓
法人の在宅医療やかかりつけ医、入院医療について知りたい方はこちら↓
在宅クリニックがなぜ病床運営をするのか、興味ある方はこちら↓
同じくなぜ在宅クリニックが訪問看護ステーション/居宅介護支援事業所をもっているのか、気になる人はこちら↓
在宅医募集しています。是非確認の上ご連絡ください↓
外来や病棟看護師、訪問看護師を募集しています。是非チェックを!↓
医療事務さん募集しています。一緒にチームの一員として働きませんか?
MSW、ケアマネさんも募集中です。是非見学にきてください↓
リハセラピストさんも募集しています。是非ご連絡を!↓
病院経営や事務長職に興味ある人募集しています。経営一緒にしませんか?↓
人事担当、SEさん募集しています。これから組織を大きく、価値のあるものにする手伝い、してくれませんか?
-